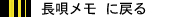四季山姥
文久二年(1862)三月
作曲 十一代目 杵屋六左衛門
作曲 十一代目 杵屋六左衛門
〈本調子〉
遠近(おちこち)の たつきも知らぬ山住まひ
我も昔は流れの身 狭き庵に見渡せば
春は殊更八重霞 その八重桐の勤めの身
柳桜をこきまぜて 都ぞ春の錦着て 手練手管に客を待つ
夏は涼しの蚊屋の内 比翼のござに月の影
秋はさながら縁先に 三味線弾いてしんき節
髪の乱れをかんざしで かき上げながら畳算
眠る禿に無理ばかり ほんにつらいぢゃないかいな
同じ思ひに啼く虫の 松虫 鈴虫くつわ虫 馬追虫のやるせなく
いづれの里に衣打つ [虫の合方]
よくも合せたものかいな
〈二上り〉
ふりさけみれば袖が浦 沖に白帆や千鳥たつ
蜆採るなる様さへも あれ遠浅に澪標(みをじるし) 松棒杭へ遁れ来て
ませた鴉が世の中を 阿呆あはうと笑ふ声
立てたる粗朶に付く海苔を
とりどりめぐる海士小舟 浮絵に見ゆる安房上総
〈三下り〉
冬は谷間に冬籠る まだ鴬の片言も
梅のつぼみの花やかに 雪を戴く葛屋の軒端
あだな松風吹き落ちて ちりやちりや ちりちりちりちりぱっと
散るは 胡蝶に似たる景色かな あら面白の山めぐり
どっこいやらぬと捕手の若木 こなたは老木の力業
中よりふっと捻ぢ切る大木 かけりかけりて谷間(たにあい)の谷の庵に妟然と
そのままそこに座をしめて 幾年月を送りけり
(歌詞は文化譜に従い、表記を一部改めた)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山姥といっても、人を喰う恐ろしい鬼女が出てくるわけではありません。
京・九条の八重桐という遊女は、武将・坂田時行の妻となります。
ところが、時行は父の敵が討てなかったことを悔い、
その無念の魂魄を八重桐の胎内に込めて自害してしまいます。
残された八重桐は足柄山へこもって山姥となり、時行の子を産み育てることを決意します。
この山姥が、本曲の主人公です。
やがて生まれた子は、全身が真っ赤で髪はぼさぼさ、猪や熊を投げ飛ばす怪力の持ち主。
怪童丸と名付けられた男の子は、後に山を訪れた源頼光の家臣に見いだされ、坂田金時と名を変えて、
〈頼光四天王〉のひとりに数えられるほどの立派な武将となりました。
さて、この怪童丸。江戸時代の中頃になると、怪力はそのままながら、
腹掛け姿でまさかりを担ぎ、熊と仲良く相撲を取る愛くるしい少年像に変化し、
名前も怪童丸ではなく〈金太郎〉と呼ばれ、親しまれるようになります。
つまり本曲は、金太郎のお母さんにあたる足柄山の山姥が、
自分が遊女であった頃を思い出しながら、四季折々に変化する廓や山中の景色を唄っている曲なのです。
日本各地に伝わる山姥伝説の中には、鬼女や鬼婆のような恐ろしい話だけでなく、
山中で産気づいた女性を助けたり、機織りをする娘を陰ながら手伝ったり、
川で溺れた子供を助けて養ったりする話もあります。
こういった山姥の持つ〈母性〉のような側面が、
「金太郎の母は山姥だった」という話が生まれた理由の一つではないでしょうか。
もっとも、本曲歌詞の中心は、山姥と金太郎ををめぐる物語ではなく、美しい四季ごとの情景です。
春・夏・秋は山姥が遊女であった頃の廓の様子、冬は山姥となって住んでいる奥深い山の様子です。
秋と冬の間にある「ふりさけ見れば……浮絵に見ゆる安房上総」は、後に補作された部分と伝えられます。
実は、しじみや海苔は一般的に春の季語です。
これらを秋と冬の間で取り上げるのは、季節の上では少しおかしいことになりますが、
廓と山の眺めの間に海の遠景が加わることで、唄全体の世界はぐっと広がっています。
なお、本曲は比較的新しい時代に成立した作品ですが、
作詞者や曲名についてはっきりしない点がいくつかあります。
歌詞についても、「袖が浦」はどこを指すのか、「若木」と「老木」は誰を例えているのか、諸説があります。
本稿では便宜上その一説を採って現代語訳を掲載していますが、これをもって決定するものではありません。
詳しくは【語句について】の各項目をご覧ください。
【こんなカンジで読んでみました】
どこがどこであるのか。それを知る手がかりもないような、深い山の、そのまた奥に住んでいます。
そんな私も、昔は遊女として勤めた身。
今、小さな庵から見渡してみると、春の八重霞に、山中の景色はことさらにじんでいます。
そう、あの頃の私は八重桐と名乗っていたっけ。
都の春を、柳と桜で織り上げた錦に例えた歌があるけれど、
私も春景色に負けないくらい豪華な錦を身にまとって、自分がついた嘘を数えてお客を待った。
夏は涼しい蚊帳の中、二枚並んでつながった茣蓙に、月の光だけが落ちていた。
秋になってそのまま月さえ見えなくなって、私はやっぱり一人きり。
縁先で三味線を爪弾けば、辛気くさい唄ばかりが浮かんで消える。
乱れた髪をかき上げたかんざし、ふと思い付いて畳に投げたら、占いにまで笑われた。
居眠りする禿のあどけない顔がむしょうに憎らしくって意地悪言って。
ごめんね。お前も私も、本当につらいものだね。
届かぬ想いをせがんでばかり、虫の鳴く音は私と同じ。
砧を打つのはどこの里だろう、遠く離れているはずなのに、不思議なくらい、淋しい音色に寄り添って。
振り返って見はるかせば、まぶしく光る袖が浦。
沖には船の白い帆。千鳥は一斉に飛び立った。
あれはなに?蜆を採っているような影まで、遠浅の海に立つ澪標みたいに、海とひとつ。
杭にとまったカラスが一羽、世間を知ったふうな声であほうあほう、ふん、お世話さま。
海の中に小枝が生えて見えるのは、海苔を育てるひびって言うのよ。
ほら、海苔をとるためにあっちこっちをめぐる小舟が見えるでしょう、
それから海の向こうには、はるか安房上総の陰までも。
今となっては、冬は谷間に籠もる日々。
鴬は覚えはじめの片言で鳴き、春はきっとまだ先のこと。
それでも、梅のつぼみがかすかな彩りを添え、
粗末な庵の軒端につもった雪がいたずらな松風に吹かれてこぼれるさまは、
ちりちりと、胡蝶が舞う景色にも似て。
なんて風流な山めぐりでしょう。
おっと行かせないぞ。立ちふさがるのは、都から怪童丸を迎えに来た若木のような若侍。
こちらは老木のような年だけれど、可愛い息子の怪童丸を真似て、力比べをしてみましょうか。
引っ張り合って真ん中からぷっつりねじ切れた大木。
私の力に驚かないで、私は山姥、この山々を飛びめぐって、
この谷間に庵を結び、ただ穏やかに長い年月を過ごしてきたのです。
これまでも、怪童丸がいなくなったこれからも。
【山姥伝説】
山姥(やまうば・やまんば)は、山中に住むという女の怪。日本各地の山に伝説・昔話が残る。
必ずしも老婆の姿ではなく、中年の女性や若い娘として伝わるものもある。
その正体は、
・山に棄てられた老婆が変じたもの(姥捨て山伝説の副産物)
・山の神に仕えた巫女が、年を経て変じたもの
・先住民族の末裔など、山間を流浪しながら暮らしていた民のこと
など、さまざまに言い伝えられてきた。
山姥伝説の内容も多岐にわたり、
例えば昔話「三枚の御札」「牛方山姥」のように、人を追いかけて喰う恐ろしい妖怪として描かれる山姥は、
〈鬼婆〉〈鬼女〉の系譜に連なるものである。
一方、機を織る娘を陰ながら手助けする話や、山姥に親切にした者に幸福が訪れる話のように、
山姥を山の神と同一視している話も多い。
また、山中で産気づいた女性が山姥に助けられた話や、川に落ちた子供を助けて養った話など、
山姥はしばしばその母性が伝えられる。山姥自身も、一度に数多くの子を産むとも伝えられる。
この母性が、浄瑠璃の類において山姥が怪童・金太郎の母に設定されたことの要因であろう。
これは多産=豊穣の神である山の神信仰の影響であり、
この点からも、山姥と山の神が同一視されていたことがうかがえる。
折口信夫は、今は一般に「姥」の字を当てる「山うば」の「うば」は、
巫女の職分の一つである「小母(うば)」と通じ、これは生まれた神の抱き守りをする役であることを
指摘している。
きびしさ・おそろしさ・ゆたかさ・あたたかさ、山姥の持つ多面的な性格は、
山という自然そのものを表しているという考えもある。
【金太郎伝説】
金太郎は、大江山酒呑童子退治・土蜘蛛退治で知られる源頼光の家臣で、四天王のひとりに数えられた
平安時代中期の武士・坂田金時(公時とも)の幼名。
武将としての坂田金時は、『今昔物語集』巻二八「頼光郎等共紫野に物を見る事」、
『古今著聞集』第九「源頼光鬼同丸を誅する事」などの説話集に名前が残る。
金時の幼名を〈金太郎〉とするようになったのは江戸時代中期の草双紙類からで、
それまでは〈怪童丸〉が一般に知られていた。
その出生は、古浄瑠璃において既に「足柄山の山姥の子」「鬼女の子」と描かれていたが、
近松門左衛門「嫗山姥」によって、
坂田時行の妻である遊女・八重桐が、夫の魂魄を受けて山姥となって産み育てた子、という話が定型化した。
父・時行の憤怒・無念の魂魄を込められて誕生した怪童丸は、
身体は朱のように赤く、産髪を乱し、熊や猪と相撲を取る異相・怪力の子として描かれたが、
時代が下り、名前が〈金太郎〉となるのと時を同じくして、腹掛けに童髪でまさかりを担いだ姿となり、
現在に伝わる金太郎像に近い快活なイメージへと変化していった。
金太郎は母・山姥とともに多くの浮世絵に描かれたが、
画題として扱われる場合、時代が下っていても名は怪童丸であることがほとんど。
近代に入り、明治二十九年(1896)に巌谷小波『日本昔噺』二〇篇として「金太郎」が刊行され、
また明治三十三年(1900)、『教科適用幼年唱歌』に童謡「キンタロー」が収められたことで、
大衆に深く親しまれるようになった。
【謡曲「山姥」と邦楽の山姥物】
歌舞伎所作事(舞踊)および邦楽には「山姥物」と称される一系統がある。
山姥の山めぐりの所作と怪童丸(後の坂田金時)の荒事を中心とするもので、
山姥物のほとんどの作品の原拠となっているのは、
謡曲「山姥」に基づく近松門左衛門の浄瑠璃「嫗山姥」である。
〈謡曲「山姥」〉
伝世阿弥作の切能。
山姥の「山めぐりの曲舞」を中心とする作品で、怪童丸(金太郎)伝説との結びつきはない。
(あらすじ)
「山姥の曲舞」を得意とし、都で百万(ひゃくま)山姥と呼ばれている遊女の一行が善光寺詣へ向かう途中、
山奥で急に日が暮れてしまった。そこへ、一人の中年の女が宿を貸そうと申し出る。
宿で、女は遊女に山姥の謡の一節を聞かせてほしいと頼み、さらに、山姥はどういう者だと思っているか、
と尋ねる。遊女が山姥は鬼女だと答えると、女は自らが山姥であることをほのめかして姿を消す。
やがて夜が更けた頃、月に照らされた深山に山姥が現れ、遊女を誘って、一緒に
山姥の境涯や山めぐりを謡った曲舞を舞い、山奥へ去っていく。
この謡曲と、坂田金時の幼少期にまつわる怪童丸伝説を組み合わせて作られたのが、
近松門左衛門の義太夫「嫗山姥」である。
〈「嫗山姥」〉
近松門左衛門作、正徳二年〔1712〕大阪竹本座初演。全五段。
八重桐の廓話が眼目なので、別名「しゃべり山姥」とも。
二段目が独立して「八重桐廓噺」として上演される。
「荻野屋八重桐」は、元禄期の名女形で地芸・所作ともにすぐれていた荻野八重桐(?~1736)
がモデルで、名もそのまま芝居に取り入れられた。
(あらすじ)
京九条の遊女・荻野屋八重桐は、北面の武士であった坂田蔵人時行と契る。
時行は父の敵討ちをもくろんでいたが、父の敵は妹の白菊が既に討ったと聞かされ、
己を恥じて自害する。
その際自分の血を八重桐に飲ませ、時行の魂魄を受けた八重桐は鬼女の怪力を授かり、
胎内の子もまた剛力を授かる。
八重桐は足柄山へ入って山姥となり、怪童丸を産み育てる。
怪童丸はやがて源頼光に見いだされて坂田金時と名乗る。
山姥物の諸作品は、すべてこの「嫗山姥」が構築した世界の枠内にあると言える。
さらに、後日譚を描いたものとして常磐津「四天王大江山入」があり、
以降の山姥物は、この曲に準拠した内容である。
〈常磐津「四天王大江山入」〉
天明五年〔1785〕江戸桐座初演。
(あらすじ)
足柄山中で怪童丸を育てている八重桐が、山樵に身をやつした源頼光家臣の三田仕と出会い、
舞を舞いながら昔の廓話をする。
三田仕が怪童丸と力比べをすると、左右から引っ張りあった松の大木が真っ二つに折れる。
仕は怪童丸を頼光へ推挙することとなり、怪童丸は坂田金時と名乗って、母である山姥と別れを惜しむ。
【語句について】
遠近の たつきも知らぬ山住まひ
謡曲「山姥」の「遠近の、たづきも知らぬ山中に、おぼつかなくも呼子鳥の、声凄き折々に(後略)」
によった表現。
和歌「遠近のたづきもしらぬ山中におぼつかなくも呼子鳥かな」(『古今和歌集』巻第一・二九・読み人しらず)
を原拠とする。
「遠近(おちこち)」は遠いところと近いところ、あちらこちら、ここかしこ。
「たつき(たづき)」は1.手がかり、よるべき手段。 2.様子・状態を知る手段。検討。
3.生活の手段。生計。 ここでは1の意で、
全体で「どこがどこであるのかも分からない、奥深い山に住んでいる」の意。
流れの身
「流れ」はさすらって生きることで、特に遊女の境遇を表す語。「流れの身」で、遊女の身の上。
「浮びもやらぬ流れのうき身」(長唄「高尾さんげ」)、
「寄する岸辺の川舟を 留めて逢瀬の波枕 世にも果敢なき流れの身」(長唄「時雨西行」)など。
春は殊更八重霞 その八重桐の勤めの身
「殊更」は1.わざと、故意に。 2.とりわけ、格別に。
「八重霞」は幾重にも深く立ち込める霞のことで、春の季語。
「桜に浮かぶ富士の雪 柳に沈む筑波山 紫匂ふ八重霞」(長唄「賤機帯」)など。
「八重」を重ねて、本曲に登場する山姥の前身である荻野屋八重桐の名を導く。
柳桜をこきまぜて 都ぞ春の錦着て
和歌「見渡せば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける」(『古今和歌集』巻第一・五六・素性法師)
を元歌とする表現。
(遊女八重桐であった頃は)都の春に例えられたような錦の衣装を着て、の意。
手練手管
「手練」「手管」はほぼ同義で、人をあやつりだます技巧、人の心を動かす手段。
特に、遊女が客をたらしこみ操る手段のことを言う。
比翼のござ(茣蓙)
二枚の茣蓙を並べて縫い合わせたもの。
並んで寝られるように作った二枚続きの茣蓙。
月の影
「影」は本来、光り輝くものを指す語。
転じて光の中に浮かび上がる姿・形、光を受けることで生じる明と暗の現象を広く表す。
日・月・灯火などについては、1.そのものが発する光。 2.そのものの姿・形。
3.そのものの光をさえぎることによって生じる陰影。 など。
ここでは、茣蓙に届く月の光。
さながら
1.そのまま、もとのまま。 2.すべて、残らず、全部。
3.(下に打消の語を伴って)まったく、全然。
4.(下に比況の語を伴って)あたかも、ちょうど、まるで(中世以降の表現)。
ここでは1で解釈するのが妥当か。
しんき節
じれったい気持ちを唄った小唄節。江戸時代後期、文化・文政頃(1804~30)に流行した俗謡。
唄の終わりに「ささ しんきえ」という囃し言葉がつく。
「野暮な力はおくの間の 浮気らしさの辛気節」(長唄「正札附」)。
「辛気」は心憂く、気重になること。
畳算
畳算は、かんざしなどを畳の上に投げ、
その落ちたところから畳の目を端まで数え、その数によって吉凶を占うもの。
特に遊里において、待ち人の訪れを占うのに行われた。
眠る禿に無理ばかり
「禿」は太夫など位の高い遊女に仕え、その見習いをする六~十四、五歳の少女。
遊女にしたがって深夜まで勤めた。
洒落本や浮世絵には、遊女のそばで眠そうにする姿や、居眠りを叱られる様子が描かれている。
ほんにつらいぢゃないかいな
「つらい」の主体を、無理を言われる禿とも、無理を言う遊女(八重桐)とも解釈できる。
本曲では続く詞章で、このつらさが秋の夜に鳴く虫と「同じ思ひ」と表現されていることを考え、
本稿では夜に人待つ身である遊女(八重桐)の嘆きとして解釈した。
同じ思ひに啼く虫の 松虫 鈴虫くつわ虫 馬追虫
秋の虫の鳴き声を、遊女である自分の身の辛さに重ねたもので、
邦楽諸曲にしばしば同類の表現が見られる。
長唄「高尾さんげ」の
「大門口の黄昏や いざ鈴虫を思ひ出す つらい勤めのその中に 可愛男を待ち兼ねて
暮松虫を思ひ出す 虫の声々かはゆらし」など。
やるせなく(やるせなし)
心のやりどころがない、思いをはらす方法がない、心が晴れない。
いづれの里に衣打つ
「いづれ」は事物の選択についての不定称の指示代名詞。どれ、どの、いつ、どこ、など。
「衣打つ」は、布や衣服を柔らかくし、つやを出すために砧(きぬた)で打つこと。
冬着の準備として秋の夜長に行われた女性の手仕事で、その音は秋の景物として古く詩歌に詠まれた。
よくも合せたものかいな
前にある「鳴く虫」の声と、衣を打つ砧の音が共に響くことか。
なお、直前に演奏される合方には二種類あり、そのひとつは砧物の音型を模したもので、
虫の音と砧の音の調和が表現され、詞章と合致する(蒲生郷昭氏論考による)。
また謡曲「山姥」において、山姥が自分と人間との関わりについて述べる場面で、
「打ちすさむ人の絶え間にも、千声万声の、砧に声のしで打つは、ただ山姥が業なれや」
(砧を打つ人が手を休めている間も、何度も砧を打っているのは、この山姥のしわざなのです)
とあるのも踏まえるか。
ふりさけみれば(振り放け見る)
はるかに仰ぎ見ると。ふり仰いで遠くを見れば。
袖が浦
関東近郊で「袖が浦」に合致するのは、
1.東京都・品川海岸の異称。 2.神奈川県小田原市国府津から二宮町にかけての海岸。
3.千葉県中西部の地名(現在の袖ヶ浦市)。 の三か所。
続く「安房上総」との整合性を考えれば3が適切だが、
「安房上総」の項で述べるように、ここでの地名は慣用的表現の一部として表出しているため、
「袖が浦」が必ずしも「上総」の地名である必要はない。
本曲の作詞者は諸説あるが、杵屋五叟氏の「「四季の山姥」の疑問」(参考文献参照)には、
御殿山の御屋敷勤めの女性が本曲作詞者であることを示す書簡についての報告があり、
その書簡中に、品川の景色を加味すれば、という内容の文言があったことが述べられている。
なお1と3ともに遠浅の海で、かつては海苔の養殖で有名な地。
沖に白帆や千鳥たつ
「白帆」「千鳥」ともに海辺の景物。
蜆(しじみ)採るなる様さへも
蜆のうち、関東で一般的なヤマトシジミは、
日本全国の河口や内湾などの汽水域(淡水と海水が混ざる低塩分の水域)に生息する。
浅い海中に立ち、袋網の口に熊手や板を付けた長い柄の漁具で採る〈蜆掻き〉が一般的。
「なる」は推定助動詞「なり」連体形。「さへ」は添加の副助詞、……までも、の意。
あれ遠浅に澪標(みをじるし)
「遠浅に見ゆ」と「澪標」を掛けた表現か。
「遠浅」は海や湖などの岸辺からかなり沖まで水の浅いこと。また、そのような岸のさま。
「澪標」は「みおつくし」とも。通行する船に水脈や推進を知らせるために目印として立てる杭。
水深の浅いところに設置することが多い。
松棒杭
前の澪標として立てている松の棒杭のことか。
ませた鴉が世の中を 阿呆あはうと笑ふ声
文意検討中。他曲にも類似の表現があると思われるが未見。
「ませる」は年齢の割に大人びる、早熟である。ここでは生意気な、といった意か。
粗朶(そだ〔しだ〕、篊〔ひび・しび〕とも)
粗朶(そだ)は海苔や牡蠣を付着させて養殖するため、海中に立てておく木おこと。
篊(ひび)は、本来は浅い海に芝や竹簀を立て並べ、一方に口を開けて、
満潮時に入った魚を干潮時に捕える漁業施設のことだが、粗朶を指して篊と呼ぶこともある。
「ひびとはひびきの略ばるべし。魚聚れば竹木の枝動くもの故ひびと云ふか。
今品川鮫洲の辺にて海苔をとるひびはもと魚を取しものなり」(『嬉遊笑覧』一二下〔1830刊〕)。
とりどりめぐる
「海苔を取り」と「とりどり」を掛けた表現。
「とりどり」は、色々、さまざま、思い思い。
浮絵
西洋の遠近画法を取り入れた浮世絵や銅版画。実景が浮き出るように見えるところから言う。
享保頃(1716~36)頃に奥村政信が創始したという。
その後流行し、覗機関(のぞきからくり)の絵にも利用された。
見ゆる(見ゆ)
ここでは見える、目に映る、といった意。
安房上総
どちらも旧国名で、安房は現在の千葉県南部、上総は現在の千葉県中央部。
ただし、本曲では実際に安房や上総が見渡せる、というわけではなく、
「浮絵に見ゆる安房上総」の詞章は、先に成立した歌舞伎「助六由縁江戸桜」中の助六の台詞
「江戸紫の鉢巻に、髪は生締め、それぇ、刷毛先の間から覗いてみろ。安房上総が浮絵のように見えるわ」
を踏まえたものと考えられる。
助六劇中のこの言い回しは広く流行し、洒落本『通言総籬』(山東京伝、天明七年〔1787〕刊)にも
「吉原本田の刷毛の間に、安房上総も近しとす」の表現がある。
まだ鴬の片言も
「片言」は、幼児などの不完全なたどたどしい言葉。また標準的な言い方から外れた訛りのある言葉。
浅春、まだ鳴きなれない鴬のたどたどしい鳴き声のこと。
花やかに(花やかなり)
形容動詞「花やかなり」の意味としては
1.きらびやかなさま、美しいさま。 2.にぎやかなさま、盛んなさま。
3.きわだっているさま、はっきりしているさま。 4.栄える様、時めくさま。
等があり、ここで最も適切なのは1.か。
また、名詞「花」に接尾語「やか」(=いかにも……らしいさま)が接続したものとも考えられる。
本稿では名詞+接尾語をとり、「(蕾なのに)いかにも花が咲いたみたいに」と解釈した。
葛屋
萱(かや)やわらなどで屋根を吹いた家。
あだな(あだなり)
「徒なり」で、1.まことのないさま、浮気なさま。 2.はかないさま、かりそめなさま。
3.むだなさま、むなしいさま。
松風
「松風」は松の梢にあたって音をたてて吹く風。
時雨や琴の音に似ているという趣向で詠まれることが多いが、本曲中では特に音に関する表現はない。
松の枝を揺らして積もった雪を散らせる風。
ちりやちりや ちりちりちりちりぱっと
長唄「汐汲」の「はんま千鳥のちりやちりちり ちりやちりちりちり ちりちりぱっと」、
長唄「賤機帯」の「沖のかもめの ちりやちりちり むらむらぱっと」のように、
本来は千鳥など、小鳥の鳴く声の表現。
本曲では、松の枝から散り落ちる雪の様を表している。
あら面白の山めぐり
「山めぐり」は山々をめぐること、特に山々の社寺を巡拝することだが、
主体が山伏などの修行者や山の精霊の場合は、超人的な力で山々を駆け巡って行を積むことを言う。
謡曲「山姥」では、終曲、山姥と遊女の舞の一節として、
「山廻りするぞ苦しき」と、人ではない山姥が山めぐりをする苦しさが次のように歌われる。
春は梢に、咲くかと待ちし、
花を尋ねて、山廻り。
秋はさやけき、影を尋ねて、
月見る方にと、山廻り。
冬は冴え行く、時雨の雲の、
雪を誘ひて、山廻り。
廻り廻りて輪廻を離れぬ、妄執の雲の、塵積って、山姥となれる、鬼女が有様、見るや見るやと、
峰に翔り、谷に響きて、今までここに、あるよと見えしが、山また山に、山廻り、
山また山に、山廻りして、行方も知らず、なりにけり。
本曲の「あら面白の山めぐり……幾年月を送りけり」の詞章は、謡曲「山姥」詞章を踏まえたうえで、
「苦しき」から「面白の」、「行方も知らず、なりにけり」から「そのままそこに座を占めて」と、
謡曲とは対照的な山姥像を描いていると考えられる。
どっこいやらぬ
「どっこい」は相手の行動をなどをさえぎり止める時に発する語。
「やる(遣る)」は行かせる。 全体で「おっと、行かせないぞ」の意。
山姥を「山めぐり」に行かせまいとする「捕手」の言葉として解釈した。
捕手の若木 こなたは老木の力業
「若木」は芽生えて間もない木、「老木」は年数を経た古木。
この詞章には、
1.若木=怪童丸、老木=源頼光の家臣
2.若木=源頼光の家臣、老木=山姥
の二通りの解釈ができる。
本詞章の原拠である常磐津「四天王大江山入」にしたがえば、怪童丸と頼光家臣の力比べの場面であるので
1.が妥当ということになるが、
前に「どっこいやらぬ」と山めぐりを止める歌詞があること、若木が「捕り手」と表現されていることから、
本稿では常磐津の趣向をいかしつつ、
怪童丸と頼光家臣の力比べを山姥と頼光家臣に転換して表現したと読み、2.で解釈した。
中よりふっと捻ぢ切る大木
常磐津「四天王大江山入」で、怪童丸と頼光の家臣が力比べのために一本の松を左右から引っ張ると、
松が中からふっつりねじ切れてしまった、という場面(「中よりふっつとねじ切って」)による。
かけりかけりて
「かける」は「翔る」で空高く飛ぶ、「駆ける」で飛ぶように速く走る。
ここでは「あら面白の山めぐり」の項で示した謡曲を原拠にしていると考えられ、
したがって山姥が主体であるので、飛び回って、の意。
妟然
妟如(あんじょ)とも。安らかなさま、落ち着いたさま。
座をしめて
座に着く、座る。ある地位・役割にずっとつく。
【成立について】
文久二年(1862)三月七日初演。
初演時の曲名は「新山姥」。
作曲十一代目杵屋六左衛門、作詞者は諸説あり。
参考文献参照のこと。
【参考文献】
河竹登志夫監修・古井戸秀夫編『歌舞伎登場人物事典』白水社、2006.5
吉川英士『邦楽鑑賞手帖』創元社、1948.8
小谷新太郎(青楓)『長唄註解』法木書店、1913.4
杵屋勝四郎・唐貝弦三『長唄新註』玄文社、1919.3
杵屋五叟「「四季の山姥」の疑問―吉川先生にお教へを乞ふ―」
『五叟遺文』1963.8(国立国会図書館蔵、非売品)所収
池田弘一「四季の山姥」『長唄びいき』青蛙房、2002.4所収
植田隆之助「長唄「四季の山姥」の内容と構成―その疑問をさぐる―」『季刊邦楽』19、1979.6
蒲生郷昭「長唄〈四季山姥〉の音楽」『季刊邦楽』19、1979.6
金子千章「豊後系浄瑠璃の山姥もの」『季刊邦楽』19、1979.6
平野健次「義太夫・地歌・荻江の山姥もの」『季刊邦楽』19、1979.6
小林責「能の「山姥」」『季刊邦楽』19、1979.6
臼田甚五郎「山姥のルーツ―民俗学的視点に立って―」『季刊邦楽』19、1979.6
乾克己ほか編『日本伝奇伝説大事典』角川書店、1986.10
小山弘志・佐藤健一郎校注・訳『新編日本古典文学全集59 謡曲集2』小学館、1998
井上信子「時代浄瑠璃『嫗山姥』」『国文学―解釈と教材の研究』第47巻第6号、2002.5
渥美清太郎編『日本戯曲全集26・続義太夫狂言時代物集』春陽堂、1931.7
黒木勘蔵校訂『日本名著全集 江戸文芸之部二八
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「長唄の会」トーク 2019.09.11
「長唄の会」トーク 2015.11.01
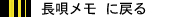
遠近(おちこち)の たつきも知らぬ山住まひ
我も昔は流れの身 狭き庵に見渡せば
春は殊更八重霞 その八重桐の勤めの身
柳桜をこきまぜて 都ぞ春の錦着て 手練手管に客を待つ
夏は涼しの蚊屋の内 比翼のござに月の影
秋はさながら縁先に 三味線弾いてしんき節
髪の乱れをかんざしで かき上げながら畳算
眠る禿に無理ばかり ほんにつらいぢゃないかいな
同じ思ひに啼く虫の 松虫 鈴虫くつわ虫 馬追虫のやるせなく
いづれの里に衣打つ [虫の合方]
よくも合せたものかいな
〈二上り〉
ふりさけみれば袖が浦 沖に白帆や千鳥たつ
蜆採るなる様さへも あれ遠浅に澪標(みをじるし) 松棒杭へ遁れ来て
ませた鴉が世の中を 阿呆あはうと笑ふ声
立てたる粗朶に付く海苔を
とりどりめぐる海士小舟 浮絵に見ゆる安房上総
〈三下り〉
冬は谷間に冬籠る まだ鴬の片言も
梅のつぼみの花やかに 雪を戴く葛屋の軒端
あだな松風吹き落ちて ちりやちりや ちりちりちりちりぱっと
散るは 胡蝶に似たる景色かな あら面白の山めぐり
どっこいやらぬと捕手の若木 こなたは老木の力業
中よりふっと捻ぢ切る大木 かけりかけりて谷間(たにあい)の谷の庵に妟然と
そのままそこに座をしめて 幾年月を送りけり
(歌詞は文化譜に従い、表記を一部改めた)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山姥といっても、人を喰う恐ろしい鬼女が出てくるわけではありません。
京・九条の八重桐という遊女は、武将・坂田時行の妻となります。
ところが、時行は父の敵が討てなかったことを悔い、
その無念の魂魄を八重桐の胎内に込めて自害してしまいます。
残された八重桐は足柄山へこもって山姥となり、時行の子を産み育てることを決意します。
この山姥が、本曲の主人公です。
やがて生まれた子は、全身が真っ赤で髪はぼさぼさ、猪や熊を投げ飛ばす怪力の持ち主。
怪童丸と名付けられた男の子は、後に山を訪れた源頼光の家臣に見いだされ、坂田金時と名を変えて、
〈頼光四天王〉のひとりに数えられるほどの立派な武将となりました。
さて、この怪童丸。江戸時代の中頃になると、怪力はそのままながら、
腹掛け姿でまさかりを担ぎ、熊と仲良く相撲を取る愛くるしい少年像に変化し、
名前も怪童丸ではなく〈金太郎〉と呼ばれ、親しまれるようになります。
つまり本曲は、金太郎のお母さんにあたる足柄山の山姥が、
自分が遊女であった頃を思い出しながら、四季折々に変化する廓や山中の景色を唄っている曲なのです。
日本各地に伝わる山姥伝説の中には、鬼女や鬼婆のような恐ろしい話だけでなく、
山中で産気づいた女性を助けたり、機織りをする娘を陰ながら手伝ったり、
川で溺れた子供を助けて養ったりする話もあります。
こういった山姥の持つ〈母性〉のような側面が、
「金太郎の母は山姥だった」という話が生まれた理由の一つではないでしょうか。
もっとも、本曲歌詞の中心は、山姥と金太郎ををめぐる物語ではなく、美しい四季ごとの情景です。
春・夏・秋は山姥が遊女であった頃の廓の様子、冬は山姥となって住んでいる奥深い山の様子です。
秋と冬の間にある「ふりさけ見れば……浮絵に見ゆる安房上総」は、後に補作された部分と伝えられます。
実は、しじみや海苔は一般的に春の季語です。
これらを秋と冬の間で取り上げるのは、季節の上では少しおかしいことになりますが、
廓と山の眺めの間に海の遠景が加わることで、唄全体の世界はぐっと広がっています。
なお、本曲は比較的新しい時代に成立した作品ですが、
作詞者や曲名についてはっきりしない点がいくつかあります。
歌詞についても、「袖が浦」はどこを指すのか、「若木」と「老木」は誰を例えているのか、諸説があります。
本稿では便宜上その一説を採って現代語訳を掲載していますが、これをもって決定するものではありません。
詳しくは【語句について】の各項目をご覧ください。
【こんなカンジで読んでみました】
どこがどこであるのか。それを知る手がかりもないような、深い山の、そのまた奥に住んでいます。
そんな私も、昔は遊女として勤めた身。
今、小さな庵から見渡してみると、春の八重霞に、山中の景色はことさらにじんでいます。
そう、あの頃の私は八重桐と名乗っていたっけ。
都の春を、柳と桜で織り上げた錦に例えた歌があるけれど、
私も春景色に負けないくらい豪華な錦を身にまとって、自分がついた嘘を数えてお客を待った。
夏は涼しい蚊帳の中、二枚並んでつながった茣蓙に、月の光だけが落ちていた。
秋になってそのまま月さえ見えなくなって、私はやっぱり一人きり。
縁先で三味線を爪弾けば、辛気くさい唄ばかりが浮かんで消える。
乱れた髪をかき上げたかんざし、ふと思い付いて畳に投げたら、占いにまで笑われた。
居眠りする禿のあどけない顔がむしょうに憎らしくって意地悪言って。
ごめんね。お前も私も、本当につらいものだね。
届かぬ想いをせがんでばかり、虫の鳴く音は私と同じ。
砧を打つのはどこの里だろう、遠く離れているはずなのに、不思議なくらい、淋しい音色に寄り添って。
振り返って見はるかせば、まぶしく光る袖が浦。
沖には船の白い帆。千鳥は一斉に飛び立った。
あれはなに?蜆を採っているような影まで、遠浅の海に立つ澪標みたいに、海とひとつ。
杭にとまったカラスが一羽、世間を知ったふうな声であほうあほう、ふん、お世話さま。
海の中に小枝が生えて見えるのは、海苔を育てるひびって言うのよ。
ほら、海苔をとるためにあっちこっちをめぐる小舟が見えるでしょう、
それから海の向こうには、はるか安房上総の陰までも。
今となっては、冬は谷間に籠もる日々。
鴬は覚えはじめの片言で鳴き、春はきっとまだ先のこと。
それでも、梅のつぼみがかすかな彩りを添え、
粗末な庵の軒端につもった雪がいたずらな松風に吹かれてこぼれるさまは、
ちりちりと、胡蝶が舞う景色にも似て。
なんて風流な山めぐりでしょう。
おっと行かせないぞ。立ちふさがるのは、都から怪童丸を迎えに来た若木のような若侍。
こちらは老木のような年だけれど、可愛い息子の怪童丸を真似て、力比べをしてみましょうか。
引っ張り合って真ん中からぷっつりねじ切れた大木。
私の力に驚かないで、私は山姥、この山々を飛びめぐって、
この谷間に庵を結び、ただ穏やかに長い年月を過ごしてきたのです。
これまでも、怪童丸がいなくなったこれからも。
【山姥伝説】
山姥(やまうば・やまんば)は、山中に住むという女の怪。日本各地の山に伝説・昔話が残る。
必ずしも老婆の姿ではなく、中年の女性や若い娘として伝わるものもある。
その正体は、
・山に棄てられた老婆が変じたもの(姥捨て山伝説の副産物)
・山の神に仕えた巫女が、年を経て変じたもの
・先住民族の末裔など、山間を流浪しながら暮らしていた民のこと
など、さまざまに言い伝えられてきた。
山姥伝説の内容も多岐にわたり、
例えば昔話「三枚の御札」「牛方山姥」のように、人を追いかけて喰う恐ろしい妖怪として描かれる山姥は、
〈鬼婆〉〈鬼女〉の系譜に連なるものである。
一方、機を織る娘を陰ながら手助けする話や、山姥に親切にした者に幸福が訪れる話のように、
山姥を山の神と同一視している話も多い。
また、山中で産気づいた女性が山姥に助けられた話や、川に落ちた子供を助けて養った話など、
山姥はしばしばその母性が伝えられる。山姥自身も、一度に数多くの子を産むとも伝えられる。
この母性が、浄瑠璃の類において山姥が怪童・金太郎の母に設定されたことの要因であろう。
これは多産=豊穣の神である山の神信仰の影響であり、
この点からも、山姥と山の神が同一視されていたことがうかがえる。
折口信夫は、今は一般に「姥」の字を当てる「山うば」の「うば」は、
巫女の職分の一つである「小母(うば)」と通じ、これは生まれた神の抱き守りをする役であることを
指摘している。
きびしさ・おそろしさ・ゆたかさ・あたたかさ、山姥の持つ多面的な性格は、
山という自然そのものを表しているという考えもある。
【金太郎伝説】
金太郎は、大江山酒呑童子退治・土蜘蛛退治で知られる源頼光の家臣で、四天王のひとりに数えられた
平安時代中期の武士・坂田金時(公時とも)の幼名。
武将としての坂田金時は、『今昔物語集』巻二八「頼光郎等共紫野に物を見る事」、
『古今著聞集』第九「源頼光鬼同丸を誅する事」などの説話集に名前が残る。
金時の幼名を〈金太郎〉とするようになったのは江戸時代中期の草双紙類からで、
それまでは〈怪童丸〉が一般に知られていた。
その出生は、古浄瑠璃において既に「足柄山の山姥の子」「鬼女の子」と描かれていたが、
近松門左衛門「嫗山姥」によって、
坂田時行の妻である遊女・八重桐が、夫の魂魄を受けて山姥となって産み育てた子、という話が定型化した。
父・時行の憤怒・無念の魂魄を込められて誕生した怪童丸は、
身体は朱のように赤く、産髪を乱し、熊や猪と相撲を取る異相・怪力の子として描かれたが、
時代が下り、名前が〈金太郎〉となるのと時を同じくして、腹掛けに童髪でまさかりを担いだ姿となり、
現在に伝わる金太郎像に近い快活なイメージへと変化していった。
金太郎は母・山姥とともに多くの浮世絵に描かれたが、
画題として扱われる場合、時代が下っていても名は怪童丸であることがほとんど。
近代に入り、明治二十九年(1896)に巌谷小波『日本昔噺』二〇篇として「金太郎」が刊行され、
また明治三十三年(1900)、『教科適用幼年唱歌』に童謡「キンタロー」が収められたことで、
大衆に深く親しまれるようになった。
【謡曲「山姥」と邦楽の山姥物】
歌舞伎所作事(舞踊)および邦楽には「山姥物」と称される一系統がある。
山姥の山めぐりの所作と怪童丸(後の坂田金時)の荒事を中心とするもので、
山姥物のほとんどの作品の原拠となっているのは、
謡曲「山姥」に基づく近松門左衛門の浄瑠璃「嫗山姥」である。
〈謡曲「山姥」〉
伝世阿弥作の切能。
山姥の「山めぐりの曲舞」を中心とする作品で、怪童丸(金太郎)伝説との結びつきはない。
(あらすじ)
「山姥の曲舞」を得意とし、都で百万(ひゃくま)山姥と呼ばれている遊女の一行が善光寺詣へ向かう途中、
山奥で急に日が暮れてしまった。そこへ、一人の中年の女が宿を貸そうと申し出る。
宿で、女は遊女に山姥の謡の一節を聞かせてほしいと頼み、さらに、山姥はどういう者だと思っているか、
と尋ねる。遊女が山姥は鬼女だと答えると、女は自らが山姥であることをほのめかして姿を消す。
やがて夜が更けた頃、月に照らされた深山に山姥が現れ、遊女を誘って、一緒に
山姥の境涯や山めぐりを謡った曲舞を舞い、山奥へ去っていく。
この謡曲と、坂田金時の幼少期にまつわる怪童丸伝説を組み合わせて作られたのが、
近松門左衛門の義太夫「嫗山姥」である。
〈「嫗山姥」〉
近松門左衛門作、正徳二年〔1712〕大阪竹本座初演。全五段。
八重桐の廓話が眼目なので、別名「しゃべり山姥」とも。
二段目が独立して「八重桐廓噺」として上演される。
「荻野屋八重桐」は、元禄期の名女形で地芸・所作ともにすぐれていた荻野八重桐(?~1736)
がモデルで、名もそのまま芝居に取り入れられた。
(あらすじ)
京九条の遊女・荻野屋八重桐は、北面の武士であった坂田蔵人時行と契る。
時行は父の敵討ちをもくろんでいたが、父の敵は妹の白菊が既に討ったと聞かされ、
己を恥じて自害する。
その際自分の血を八重桐に飲ませ、時行の魂魄を受けた八重桐は鬼女の怪力を授かり、
胎内の子もまた剛力を授かる。
八重桐は足柄山へ入って山姥となり、怪童丸を産み育てる。
怪童丸はやがて源頼光に見いだされて坂田金時と名乗る。
山姥物の諸作品は、すべてこの「嫗山姥」が構築した世界の枠内にあると言える。
さらに、後日譚を描いたものとして常磐津「四天王大江山入」があり、
以降の山姥物は、この曲に準拠した内容である。
〈常磐津「四天王大江山入」〉
天明五年〔1785〕江戸桐座初演。
(あらすじ)
足柄山中で怪童丸を育てている八重桐が、山樵に身をやつした源頼光家臣の三田仕と出会い、
舞を舞いながら昔の廓話をする。
三田仕が怪童丸と力比べをすると、左右から引っ張りあった松の大木が真っ二つに折れる。
仕は怪童丸を頼光へ推挙することとなり、怪童丸は坂田金時と名乗って、母である山姥と別れを惜しむ。
【語句について】
遠近の たつきも知らぬ山住まひ
謡曲「山姥」の「遠近の、たづきも知らぬ山中に、おぼつかなくも呼子鳥の、声凄き折々に(後略)」
によった表現。
和歌「遠近のたづきもしらぬ山中におぼつかなくも呼子鳥かな」(『古今和歌集』巻第一・二九・読み人しらず)
を原拠とする。
「遠近(おちこち)」は遠いところと近いところ、あちらこちら、ここかしこ。
「たつき(たづき)」は1.手がかり、よるべき手段。 2.様子・状態を知る手段。検討。
3.生活の手段。生計。 ここでは1の意で、
全体で「どこがどこであるのかも分からない、奥深い山に住んでいる」の意。
流れの身
「流れ」はさすらって生きることで、特に遊女の境遇を表す語。「流れの身」で、遊女の身の上。
「浮びもやらぬ流れのうき身」(長唄「高尾さんげ」)、
「寄する岸辺の川舟を 留めて逢瀬の波枕 世にも果敢なき流れの身」(長唄「時雨西行」)など。
春は殊更八重霞 その八重桐の勤めの身
「殊更」は1.わざと、故意に。 2.とりわけ、格別に。
「八重霞」は幾重にも深く立ち込める霞のことで、春の季語。
「桜に浮かぶ富士の雪 柳に沈む筑波山 紫匂ふ八重霞」(長唄「賤機帯」)など。
「八重」を重ねて、本曲に登場する山姥の前身である荻野屋八重桐の名を導く。
柳桜をこきまぜて 都ぞ春の錦着て
和歌「見渡せば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける」(『古今和歌集』巻第一・五六・素性法師)
を元歌とする表現。
(遊女八重桐であった頃は)都の春に例えられたような錦の衣装を着て、の意。
手練手管
「手練」「手管」はほぼ同義で、人をあやつりだます技巧、人の心を動かす手段。
特に、遊女が客をたらしこみ操る手段のことを言う。
比翼のござ(茣蓙)
二枚の茣蓙を並べて縫い合わせたもの。
並んで寝られるように作った二枚続きの茣蓙。
月の影
「影」は本来、光り輝くものを指す語。
転じて光の中に浮かび上がる姿・形、光を受けることで生じる明と暗の現象を広く表す。
日・月・灯火などについては、1.そのものが発する光。 2.そのものの姿・形。
3.そのものの光をさえぎることによって生じる陰影。 など。
ここでは、茣蓙に届く月の光。
さながら
1.そのまま、もとのまま。 2.すべて、残らず、全部。
3.(下に打消の語を伴って)まったく、全然。
4.(下に比況の語を伴って)あたかも、ちょうど、まるで(中世以降の表現)。
ここでは1で解釈するのが妥当か。
しんき節
じれったい気持ちを唄った小唄節。江戸時代後期、文化・文政頃(1804~30)に流行した俗謡。
唄の終わりに「ささ しんきえ」という囃し言葉がつく。
「野暮な力はおくの間の 浮気らしさの辛気節」(長唄「正札附」)。
「辛気」は心憂く、気重になること。
畳算
畳算は、かんざしなどを畳の上に投げ、
その落ちたところから畳の目を端まで数え、その数によって吉凶を占うもの。
特に遊里において、待ち人の訪れを占うのに行われた。
眠る禿に無理ばかり
「禿」は太夫など位の高い遊女に仕え、その見習いをする六~十四、五歳の少女。
遊女にしたがって深夜まで勤めた。
洒落本や浮世絵には、遊女のそばで眠そうにする姿や、居眠りを叱られる様子が描かれている。
ほんにつらいぢゃないかいな
「つらい」の主体を、無理を言われる禿とも、無理を言う遊女(八重桐)とも解釈できる。
本曲では続く詞章で、このつらさが秋の夜に鳴く虫と「同じ思ひ」と表現されていることを考え、
本稿では夜に人待つ身である遊女(八重桐)の嘆きとして解釈した。
同じ思ひに啼く虫の 松虫 鈴虫くつわ虫 馬追虫
秋の虫の鳴き声を、遊女である自分の身の辛さに重ねたもので、
邦楽諸曲にしばしば同類の表現が見られる。
長唄「高尾さんげ」の
「大門口の黄昏や いざ鈴虫を思ひ出す つらい勤めのその中に 可愛男を待ち兼ねて
暮松虫を思ひ出す 虫の声々かはゆらし」など。
やるせなく(やるせなし)
心のやりどころがない、思いをはらす方法がない、心が晴れない。
いづれの里に衣打つ
「いづれ」は事物の選択についての不定称の指示代名詞。どれ、どの、いつ、どこ、など。
「衣打つ」は、布や衣服を柔らかくし、つやを出すために砧(きぬた)で打つこと。
冬着の準備として秋の夜長に行われた女性の手仕事で、その音は秋の景物として古く詩歌に詠まれた。
よくも合せたものかいな
前にある「鳴く虫」の声と、衣を打つ砧の音が共に響くことか。
なお、直前に演奏される合方には二種類あり、そのひとつは砧物の音型を模したもので、
虫の音と砧の音の調和が表現され、詞章と合致する(蒲生郷昭氏論考による)。
また謡曲「山姥」において、山姥が自分と人間との関わりについて述べる場面で、
「打ちすさむ人の絶え間にも、千声万声の、砧に声のしで打つは、ただ山姥が業なれや」
(砧を打つ人が手を休めている間も、何度も砧を打っているのは、この山姥のしわざなのです)
とあるのも踏まえるか。
ふりさけみれば(振り放け見る)
はるかに仰ぎ見ると。ふり仰いで遠くを見れば。
袖が浦
関東近郊で「袖が浦」に合致するのは、
1.東京都・品川海岸の異称。 2.神奈川県小田原市国府津から二宮町にかけての海岸。
3.千葉県中西部の地名(現在の袖ヶ浦市)。 の三か所。
続く「安房上総」との整合性を考えれば3が適切だが、
「安房上総」の項で述べるように、ここでの地名は慣用的表現の一部として表出しているため、
「袖が浦」が必ずしも「上総」の地名である必要はない。
本曲の作詞者は諸説あるが、杵屋五叟氏の「「四季の山姥」の疑問」(参考文献参照)には、
御殿山の御屋敷勤めの女性が本曲作詞者であることを示す書簡についての報告があり、
その書簡中に、品川の景色を加味すれば、という内容の文言があったことが述べられている。
なお1と3ともに遠浅の海で、かつては海苔の養殖で有名な地。
沖に白帆や千鳥たつ
「白帆」「千鳥」ともに海辺の景物。
蜆(しじみ)採るなる様さへも
蜆のうち、関東で一般的なヤマトシジミは、
日本全国の河口や内湾などの汽水域(淡水と海水が混ざる低塩分の水域)に生息する。
浅い海中に立ち、袋網の口に熊手や板を付けた長い柄の漁具で採る〈蜆掻き〉が一般的。
「なる」は推定助動詞「なり」連体形。「さへ」は添加の副助詞、……までも、の意。
あれ遠浅に澪標(みをじるし)
「遠浅に見ゆ」と「澪標」を掛けた表現か。
「遠浅」は海や湖などの岸辺からかなり沖まで水の浅いこと。また、そのような岸のさま。
「澪標」は「みおつくし」とも。通行する船に水脈や推進を知らせるために目印として立てる杭。
水深の浅いところに設置することが多い。
松棒杭
前の澪標として立てている松の棒杭のことか。
ませた鴉が世の中を 阿呆あはうと笑ふ声
文意検討中。他曲にも類似の表現があると思われるが未見。
「ませる」は年齢の割に大人びる、早熟である。ここでは生意気な、といった意か。
粗朶(そだ〔しだ〕、篊〔ひび・しび〕とも)
粗朶(そだ)は海苔や牡蠣を付着させて養殖するため、海中に立てておく木おこと。
篊(ひび)は、本来は浅い海に芝や竹簀を立て並べ、一方に口を開けて、
満潮時に入った魚を干潮時に捕える漁業施設のことだが、粗朶を指して篊と呼ぶこともある。
「ひびとはひびきの略ばるべし。魚聚れば竹木の枝動くもの故ひびと云ふか。
今品川鮫洲の辺にて海苔をとるひびはもと魚を取しものなり」(『嬉遊笑覧』一二下〔1830刊〕)。
とりどりめぐる
「海苔を取り」と「とりどり」を掛けた表現。
「とりどり」は、色々、さまざま、思い思い。
浮絵
西洋の遠近画法を取り入れた浮世絵や銅版画。実景が浮き出るように見えるところから言う。
享保頃(1716~36)頃に奥村政信が創始したという。
その後流行し、覗機関(のぞきからくり)の絵にも利用された。
見ゆる(見ゆ)
ここでは見える、目に映る、といった意。
安房上総
どちらも旧国名で、安房は現在の千葉県南部、上総は現在の千葉県中央部。
ただし、本曲では実際に安房や上総が見渡せる、というわけではなく、
「浮絵に見ゆる安房上総」の詞章は、先に成立した歌舞伎「助六由縁江戸桜」中の助六の台詞
「江戸紫の鉢巻に、髪は生締め、それぇ、刷毛先の間から覗いてみろ。安房上総が浮絵のように見えるわ」
を踏まえたものと考えられる。
助六劇中のこの言い回しは広く流行し、洒落本『通言総籬』(山東京伝、天明七年〔1787〕刊)にも
「吉原本田の刷毛の間に、安房上総も近しとす」の表現がある。
まだ鴬の片言も
「片言」は、幼児などの不完全なたどたどしい言葉。また標準的な言い方から外れた訛りのある言葉。
浅春、まだ鳴きなれない鴬のたどたどしい鳴き声のこと。
花やかに(花やかなり)
形容動詞「花やかなり」の意味としては
1.きらびやかなさま、美しいさま。 2.にぎやかなさま、盛んなさま。
3.きわだっているさま、はっきりしているさま。 4.栄える様、時めくさま。
等があり、ここで最も適切なのは1.か。
また、名詞「花」に接尾語「やか」(=いかにも……らしいさま)が接続したものとも考えられる。
本稿では名詞+接尾語をとり、「(蕾なのに)いかにも花が咲いたみたいに」と解釈した。
葛屋
萱(かや)やわらなどで屋根を吹いた家。
あだな(あだなり)
「徒なり」で、1.まことのないさま、浮気なさま。 2.はかないさま、かりそめなさま。
3.むだなさま、むなしいさま。
松風
「松風」は松の梢にあたって音をたてて吹く風。
時雨や琴の音に似ているという趣向で詠まれることが多いが、本曲中では特に音に関する表現はない。
松の枝を揺らして積もった雪を散らせる風。
ちりやちりや ちりちりちりちりぱっと
長唄「汐汲」の「はんま千鳥のちりやちりちり ちりやちりちりちり ちりちりぱっと」、
長唄「賤機帯」の「沖のかもめの ちりやちりちり むらむらぱっと」のように、
本来は千鳥など、小鳥の鳴く声の表現。
本曲では、松の枝から散り落ちる雪の様を表している。
あら面白の山めぐり
「山めぐり」は山々をめぐること、特に山々の社寺を巡拝することだが、
主体が山伏などの修行者や山の精霊の場合は、超人的な力で山々を駆け巡って行を積むことを言う。
謡曲「山姥」では、終曲、山姥と遊女の舞の一節として、
「山廻りするぞ苦しき」と、人ではない山姥が山めぐりをする苦しさが次のように歌われる。
春は梢に、咲くかと待ちし、
花を尋ねて、山廻り。
秋はさやけき、影を尋ねて、
月見る方にと、山廻り。
冬は冴え行く、時雨の雲の、
雪を誘ひて、山廻り。
廻り廻りて輪廻を離れぬ、妄執の雲の、塵積って、山姥となれる、鬼女が有様、見るや見るやと、
峰に翔り、谷に響きて、今までここに、あるよと見えしが、山また山に、山廻り、
山また山に、山廻りして、行方も知らず、なりにけり。
本曲の「あら面白の山めぐり……幾年月を送りけり」の詞章は、謡曲「山姥」詞章を踏まえたうえで、
「苦しき」から「面白の」、「行方も知らず、なりにけり」から「そのままそこに座を占めて」と、
謡曲とは対照的な山姥像を描いていると考えられる。
どっこいやらぬ
「どっこい」は相手の行動をなどをさえぎり止める時に発する語。
「やる(遣る)」は行かせる。 全体で「おっと、行かせないぞ」の意。
山姥を「山めぐり」に行かせまいとする「捕手」の言葉として解釈した。
捕手の若木 こなたは老木の力業
「若木」は芽生えて間もない木、「老木」は年数を経た古木。
この詞章には、
1.若木=怪童丸、老木=源頼光の家臣
2.若木=源頼光の家臣、老木=山姥
の二通りの解釈ができる。
本詞章の原拠である常磐津「四天王大江山入」にしたがえば、怪童丸と頼光家臣の力比べの場面であるので
1.が妥当ということになるが、
前に「どっこいやらぬ」と山めぐりを止める歌詞があること、若木が「捕り手」と表現されていることから、
本稿では常磐津の趣向をいかしつつ、
怪童丸と頼光家臣の力比べを山姥と頼光家臣に転換して表現したと読み、2.で解釈した。
中よりふっと捻ぢ切る大木
常磐津「四天王大江山入」で、怪童丸と頼光の家臣が力比べのために一本の松を左右から引っ張ると、
松が中からふっつりねじ切れてしまった、という場面(「中よりふっつとねじ切って」)による。
かけりかけりて
「かける」は「翔る」で空高く飛ぶ、「駆ける」で飛ぶように速く走る。
ここでは「あら面白の山めぐり」の項で示した謡曲を原拠にしていると考えられ、
したがって山姥が主体であるので、飛び回って、の意。
妟然
妟如(あんじょ)とも。安らかなさま、落ち着いたさま。
座をしめて
座に着く、座る。ある地位・役割にずっとつく。
【成立について】
文久二年(1862)三月七日初演。
初演時の曲名は「新山姥」。
作曲十一代目杵屋六左衛門、作詞者は諸説あり。
参考文献参照のこと。
【参考文献】
河竹登志夫監修・古井戸秀夫編『歌舞伎登場人物事典』白水社、2006.5
吉川英士『邦楽鑑賞手帖』創元社、1948.8
小谷新太郎(青楓)『長唄註解』法木書店、1913.4
杵屋勝四郎・唐貝弦三『長唄新註』玄文社、1919.3
杵屋五叟「「四季の山姥」の疑問―吉川先生にお教へを乞ふ―」
『五叟遺文』1963.8(国立国会図書館蔵、非売品)所収
池田弘一「四季の山姥」『長唄びいき』青蛙房、2002.4所収
植田隆之助「長唄「四季の山姥」の内容と構成―その疑問をさぐる―」『季刊邦楽』19、1979.6
蒲生郷昭「長唄〈四季山姥〉の音楽」『季刊邦楽』19、1979.6
金子千章「豊後系浄瑠璃の山姥もの」『季刊邦楽』19、1979.6
平野健次「義太夫・地歌・荻江の山姥もの」『季刊邦楽』19、1979.6
小林責「能の「山姥」」『季刊邦楽』19、1979.6
臼田甚五郎「山姥のルーツ―民俗学的視点に立って―」『季刊邦楽』19、1979.6
乾克己ほか編『日本伝奇伝説大事典』角川書店、1986.10
小山弘志・佐藤健一郎校注・訳『新編日本古典文学全集59 謡曲集2』小学館、1998
井上信子「時代浄瑠璃『嫗山姥』」『国文学―解釈と教材の研究』第47巻第6号、2002.5
渥美清太郎編『日本戯曲全集26・続義太夫狂言時代物集』春陽堂、1931.7
黒木勘蔵校訂『日本名著全集 江戸文芸之部二八
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「長唄の会」トーク 2019.09.11
「長唄の会」トーク 2015.11.01